ストレスの仕組みは理解できましたか。今回は、個人の受け取り方による違いに触れます。
心理学者のR・S・ラザルスは、「ストレスがあっても、受け手がストレスをどのように評価(認知)するかによってストレスが異なる」と述べています。
受け手の判断によって、ストレスかどうかは異なる
人は、ストレッサーについて、身を守るためにそれが自分にとって有害かどうかを判断(認知)します。そもそもその人にとってストレッサーが「有害ではない」と判断されれば、ストレスは生じません。
ここで有害と判断された場合は、次の段階に入ります。そして、その事態に対処する「効果的な方法を知っているか」「その効果的な方法を実行できるか」をチェックします。結果的に「対処できる」と判断した場合には、ストレスは緩和され、「対処できない」としたときにはストレスは高まります。
過去に同様のストレスを乗り越えた経験があれば、あまり大きなストレスになりませんが、まったく初めてならば不安感が増し、大きなストレスになります。こうしてストレスに対する経験や対処能力の有無によって、ストレスを受けるかどうかが決まります。
ラザルスの理論では、心理的ストレス反応を決めるものは、
「ストレッサーを有害なものと認知するか」と「適切な対処の有無(コーピング)」なのです。
小さなストレスの積み重ねに注目
ラザルスは、人生上の大きな出来事よりも、日々の生活で持続する小さなイライラがストレスになるとも考えました。
例えば、離婚や解雇という大きなライフイベントよりも、人間関係のちょっとしたトラブルや通勤の混雑、勉強や家事のつまづきなどが、大きなストレス要因を形成するのです。
この小さなストレスの積み重ねが心身の健康に影響を与えるという考え方は、気付かずにストレスをためこんで病気になってしまわないよう、日々の対処が必要だと教えてくれます。日常生活でできる対処については、後のレッスンでいくつかご紹介します。
この他に、ストレスを理解する上で大切な、いくつかのヒントを解説します。
ストレス要因と気づかないものもある
ストレス要因には、「急性」と「慢性」があります。
例えば、地震は突然起こり、急性のストレスを引き起こします。予測できないため衝撃が大きくなります。
一方、その後の避難生活は慢性のストレスとなります。慢性のストレス要因は、じわじわと始まり、ひとつひとつの出来事は小さくても、積もれば健康を脅かす存在にもなり得るものです。
本人は気付かなくても、突然、原因不明のストレス病を発症する場合もあるので要注意です。周囲が見守り、必要ならば声かけしましょう。本人が、「ストレスを感じている」ことを自覚しなければならないケースがあります。
ストレスは重なり、つながる
仕事の失敗で落ち込み、集中力が落ちてさらに失敗し、周囲に責められ、欠勤や遅刻につながる・・・。ストレス要因により、心身の状態が落ちることで、次のストレス要因が発生しやすくなります。
神経質になり、気が滅入っているため、普段は気にしないことにも鋭く反応してしまいます。いつもより、「つらさ」を感じやすい状態が長く続き、すべての出来事がいっそうつらく感じ、引きこもってしまう場合もあります。
自分では何が原因か思い出せなくなっているかもしれません。
そんな時は、第三者の力を借りて、出来事を整理してみましょう。ここだ、というポイントがわかり、案外簡単な解決方法が思い浮かぶかもしれません。
医師やカウンセラーは、話を聞き出し整理する方法を知るプロですので、彼らに頼るのも良いでしょう。
予測して備えれば、ストレス要因は減らすことができる
いきなり不意打ちをくらうと、ショックが大きいですよね。地震への備えと同じで、事前に予測し、対処方法を考えておきましょう。
例えば、明日のプレゼンの緊張で眠れない、失敗したらと不安でたまらないという場合。成功イメージを描けるまで練習する、質疑応答を予想して答える訓練をすることで、自分への打撃もストレス要因も減らせます。
本来、ストレス対策は「事前に行うもの」であり、もぐらたたきのように「事後に慌てて行うもの」ではないのです。
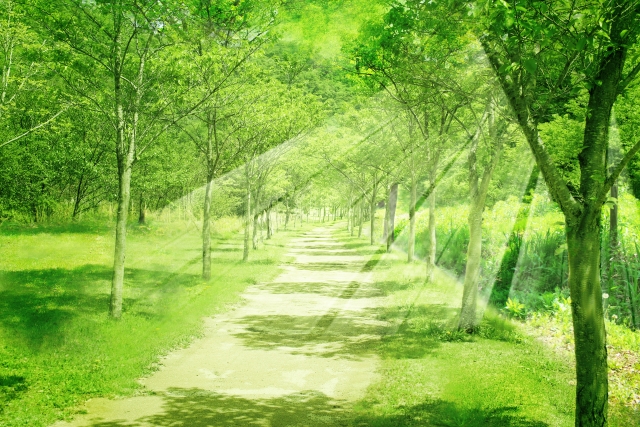
Lesson1-4 まとめ
- 受け手の判断により、ストレスかどうかは異なる
- 小さなストレスの積み重ねが、大きな影響を与えることもある
- ストレス要因には急性と慢性があり、気づかないものもある
- ストレスは重なり、つながる
- 予測して備えれば、ストレス要因は減らすことができる