ストレス予防
職場のストレスは、仕事量や残業時間を減らせば減らせるのでしょうか?
職業性ストレス研究の第一人者である心理学者Karasek(カルセック)は「裁量権と仕事量モデル」を提唱しました。
もっとも活性度が高い(本人がやりがいと充実感を感じる)のは、仕事量が多く裁量権が大きい場合です。
最もストレスが高いのは、仕事量が多く、裁量権が小さい場合です。
つまり、20代の若い労働者は、40代に比べ量的な負担感は弱いものの、役割分担や意思決定が不明確という質的な負担をストレスと感じやすいのです。
結論は、仕事量を減らすだけでは、職場のストレスは減りません。家庭でも同じことが言えるでしょう。
仕事量を減らさずに、心の健康問題を減らす鍵は、達成感と裁量権にあります。
管理監督者の労務管理に関する理解と、人材マネジメント・モチベーション管理の重要性を認識しているかにかかっています。
管理監督者本人の能力が低く、先を見通せない人は、部下に仕事を任せられず裁量権を奪ってしまいますし、自分自身が仕事の意味を見出せない管理監督者は部下に希望ややる気を持たせることができません。
管理監督者の生き方・働き方が、部下のメンタルヘルスに大きな影響を与えるという構造です。
法的な注意点
とはいうものの、限界的長時間労働には注意が必要です。
時間外・休日労働に関わる36協定(労働基準法36条に基づく労使協定)を順守しながら、以下の時間は労災認定される確率が高いものと認識すべきです。
これは最悪のケースですので、このラインに近づかないよう、普段から業務プロセス改革などに取り組みましょう。
・1か月間に160時間以上の時間外労働
・連続した2カ月間に120時間/月以上の時間外労働
・連続した3か月間に100時間/月以上の時間外労働
また、セクハラやパワハラにあたる行為が行われていないか、職場を観察する必要もあります。精神障害の労災認定のうち13%(2011年)がパワハラによるものです。普段のコミュニケーションも大切です。
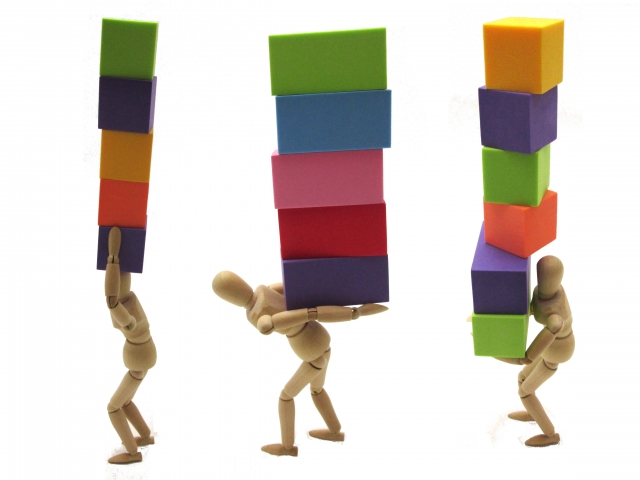
まとめ
・仕事量を減らすだけでは、職場のストレスは減らない。
・仕事量を減らさずに、心の健康問題を減らす鍵は、達成感と裁量権にある。管理監督者の労務管理に関する理解と、人材マネジメント・モチベーション管理の重要性を認識しているかが重要。
・時間外・休日労働に関わる36協定(労働基準法36条に基づく労使協定)を遵守する。